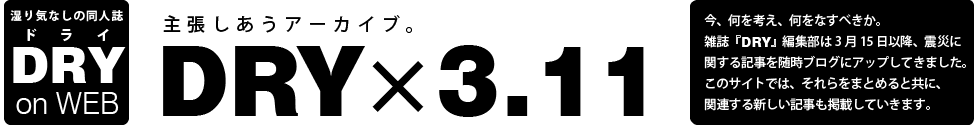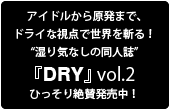福島・Jヴィレッジ――原発作業の最前線は ◎4月23日◎

首の落ちた地蔵――浪江町から楢葉町

(Googleマップより作成)
4月23日、『DRY』編集部の上航、ヨッケ・コンドオ、斉藤光平とともに二度目の福島取材をこころみた。深夜バスで郡山まで行き、レンタカーで午前中に「DASH村」があるとされる浪江町へ向かう。しかし、この計画は原発20キロ圏内直前の検問により頓挫、次に楢葉町のJヴィレッジへ向かった。 Jヴィレッジは日本初のサッカーのナショナルトレーニングセンターだが、東電が一部出資していたこともあって今回の原発事故対応の前線基地となっている。 浪江町から楢葉町へは、本来ならば南東方向へ進めば1時間足らずで到着できるのだが、ところどころ原発20キロ圏内につき警戒区域として立ち入りが禁止されていたため迂回を余儀なくされ、二時間ほどかかってしまった。
Jヴィレッジへ向かう最中、いわき市内にある詩人・草野心平の生家を通った。当然のごとく観覧は臨時休止となっているが、5月3日に再開予定だそう(草野心平記念文学館、草野心平生家は予定通り5月3日から再開し、草野心平記念文学館は6月30日まで無料で観覧可)。 また、楢葉町の南にある広野町を通過して地震と津波の被害を実見したが、津波の被害を辛うじて免れた高台でさえ、ブロック塀が崩れ、瓦が落ちてしまった建物がいたるところに見られる。特に、首から上がもげてしまってそのまま風雨にさらされているお地蔵さんが痛々しかった。
全国各地のナンバープレート
まず、我々はJヴィレッジスタジアムのある施設の南側へ入った(地図①)。駐車場には十数台のトラックが並んでいるが、人気は全くない。建設会社のものがほとんどで、浜松、福井、室蘭、三重。ナンバープレートをみるだけで、全国各地からこの車が集結していることがわかる。 各車両のフロントガラスには「東京電力支援 緊急支援車両」「工業用水運搬作業従事車両」「負けないぞ! 福島」などのカードが貼られている。
話は遡るが、4月上旬に南相馬市を訪れた際、ヨッシーランド付近で瓦礫の除去作業をしていたある建設会社は北海道の会社だった。社長に話をうかがうと、全国各地から動かせる重機が集結しており、Jヴィレッジからやって来た系列会社の作業員もいるという。 このように、Jヴィレッジは原発事故の対応作業のみならず、被災地復旧のために全国各地から集められた重機や作業員の拠点となっている。

さて、トレーニング施設は作業員のための仮の宿泊所になっており、窓から内部の様子を確認したところ、ところどころに畳まれた布団や無造作に脱ぎ捨てられたサンダルがみえた。作業員の過酷な生活環境がうかがわれた。
防護服での除染作業

次に、Jヴィレッジの広い敷地を迂回して、北側の人工芝フィールドやホテル、レストラン、メディカルセンターなど主要施設の集まるエリアへ向かった(地図②)。 人気が全くなかった南側のエリアに比べ、こちらはたくさんの人々が慌ただしく動き回っており、ものものしい雰囲気だ。レンタカーに加え何の通行手形も持たない我々だったが、意外にすんなりと敷地に入ることができた。

トラックや重機ばかりが停まっていた南側のエリアに比べて、こちらの駐車場には乗用車や自衛隊のジープ、アンテナを搭載した電話会社の車両など多様な車がみられた。駐車場の傍らには防護服を着た一団が集まって、車両の除染作業の最中だった。 足場を組んで高いところからも高圧洗浄を行えるようにし、放射性物質を除去する。高所作業車やミキサー車、ワゴン車などがみられたが、原発まで相当に近づいて何らかの作業をしていたのだろう。

図らずも原発20キロ圏内へ
東京電力の社員にJヴィレッジの内部の様子について取材をこころみたところ、「ただいま担当者を呼んでまいります」とのこと。大体予想していたことではあるが、やって来た担当者は「申し訳ありませんが、私どもからは申し上げることができません。詳しいことは本社にお尋ねください」とのこと。 実は、このとき我々がいたJヴィレッジの北側エリアの一部はすでに原発20キロ圏内に含まれており、一刻も早く退去するよう指示された。ちなみに、このあと我々はいわき市の小名浜にあるソープ街へ向かった。これについては斉藤光平の取材記事があるので、併せてご参照いただきたい。

しかし、ガイガーカウンターの値は0.9マイクロシーベルトで、予想していたほど高くない。むしろ、浪江町の20キロ圏外で出た4.1マイクロシーベルトの方がはるかに高かった。最近は各地で計測される放射線のデータ公表も進んでいるが、 結局のところ「20キロ圏」という線引きは必ずしも放射線の影響を反映して設定されたものではないのだ。これは緊急の難指示や当座の補償のためなど、行政上の便宜が考慮された面も大きいはずだ。 しかし、長期的な視野で見た場合に必ずしも直接的、間接的含め原発事故の被害を正確に反映したわけではない「20キロ圏」や「30キロ圏」という境界が、生活の安全性や補償の問題として今後ますます浮上してくるだろうことは明白だ。
原発作業の最前線を知りたければJヴィレッジへ
3月11日の震災後、記者会見でみられた東京電力の原発事故の対応作業や、計画停電に関する受け答えにはどこか見ていてもどかしいところがあった。頻繁に下を向いて手にしたペーパーを確認したり、「詳しい話は担当者に確認します」と質問に対して明確な答えを述べなかったり、という具合に。
しかし、記者会見の場でいくら東京電力の上層部を詰問したところで、引き出せる情報には限界がある。なぜなら、彼らはあくまで原発を管理することが主な仕事なのであって、実際に原発を現場で動かしているのはその下請け、孫請けの会社であるからだ。現場を知らない人間にいくら現場がどうなっているか聞いたところで埒が明かない。
もちろん、私は原発事故に関わる東電の対応を擁護する気はない。しかし、情報の不十分さをすべて東電の対応の悪さのせいにして、これを執拗に責め立てる一部のメディアもいかがなものか。
4月上旬に斉藤光平と共に南相馬市を訪れた際には、東京電力の体質や内部事情を知る方から、もし原発事故の対応の最前線を知りたかったらJヴィレッジに取材へ行くのが早いだろうとうかがった。 このとき、南相馬市で出会ったカメラマンの飯田勇氏とフリージャーナリストの西牟田靖氏はさっそくJヴィレッジへ向かい、そこで働く人々の様子をリポートしている (飯田氏の記事はグラビアと共に4月14日発売の『週刊文春』に掲載、西牟田氏は5月5日の「ニコニコ生放送 カメラが震えた!ジャーナリストが撮った原発と被災地」に出演)。
キーワードは「長期化」か

結局、今回の取材では原発作業の進展について有益な情報を得ることは出来なかったが、その作業に従事する人たちの姿を垣間見ることはできた。Jヴィッレジ内の喫煙所で一服していた某大手建設会社のOさんに話をうかがった。彼はこの付近の道路復旧作業のために来ている。 一日8時間労働だが、放射線量はあまり気にしていない。ここには自分では把握しきれないほどの人数が集まっていて、一日の作業工程の指示や宿泊場所の手配はすべて会社ごとに行われるそうだ。
原発事故の収束作業に従事する人々は「フクシマ50」と命名されて称賛を浴びていたが、原子炉の冷却以外にもやらなければならないことは多い。Oさんのような道路の復旧作業もその一つだ。Jヴィレッジ付近には震災のために大きく崩れた道路もある(写真は地図の赤丸で示した地点で撮影)。
Jヴィレッジ近辺の放射線量は比較的高くないが、それでも今後こうした作業が長期化することを考えれば、いかに労働力を確保していくか対策を講じていかなければ労働力不足にもなりかねない。 実際、5月下旬の時点で大阪の西成では原発作業に関わる労働力不足を見越して、西成の日雇い労働者が原発作業に従事することになった場合の注意点を呼び掛けている(「大阪・西成のドヤ街と東日本大震災」参照)。
震災の避難生活にせよ、原発の収束作業にせよ、今後は長期化に伴う集団生活の限界や労働力不足など、様々な問題に対処していかなければならない。震災から三ヶ月近くが経ち、被災地支援をよびかける声は相対的に少なくなった観は否めない。 そろそろ被災地ごとに復旧、復興のペースの差が如実に表れ始め、複雑な想いでおられる方も多いかと思う。首都圏で日々の生活を営む我々は喉元過ぎて熱さを忘れるのでなく、せめて「本当に大変なのはこれから」という意識を持っておきたい。
(文責 : 稲葉秀朗 | 写真 : 上航、斉藤光平、稲葉秀朗)