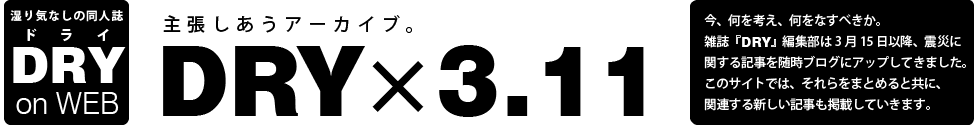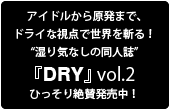茨城・取手市の避難所ではいま ◎5月7日◎
東日本大震災の発生から二ヶ月が経つ。行き過ぎとさえ言われた自粛ムードも去り、各所での節電を除けば東京の街並みは賑わいを取り戻しつつあるようにみえる。しかし、今この瞬間も避難生活を続けている人々は大勢おり、それは必ずしも被災地に限ったことではない。
茨城県南部に位置する取手市は古くから水戸街道沿いの宿場町として栄え、新歌舞伎の『一本刀土俵入』の舞台としても有名だ。水戸街道はいまの国道6号線で、北上していくと福島第一原発のある福島県双葉町へも続いている。 昨年12月には取手駅前に停車中のバス内で無差別刺傷事件が発生したことも記憶に新しい。
東日本大震災発生後、取手市は市内の施設を避難所として開放した。3月20日には同市の姉妹都市である福島県南相馬市の住民が到着し、現在も避難所生活を続けている。余談になるが、取手市を含む茨城県南部は鎌倉時代に相馬氏という一族が支配していたため、北相馬とよばれていた。 のちに分裂した相馬氏の一派は現在の福島県へ移り、これが福島県相馬市や南相馬市の名前の由来となる。このように、取手市は南相馬市の歴史的なつながりも姉妹都市協定に関係しているらしい。

避難所となっている取手競輪場選手宿泊施設の外観。

子供服を探す夫婦。
5月7日、私は避難所のひとつである取手競輪場の選手宿泊所を訪れた。競輪場と隣接する宿泊所は共に小高い丘の上にあり、見晴らしがいい。
1階のロビーは公共スペースとなっており、長机の上に福島県の地方紙を含む各種新聞や、近隣での求人広告が所狭しと置かれている。ホワイトボードは施設からの告知や付近の病院の出張診察の情報で埋め尽くされている。 南相馬市で営業している店舗や病院の情報も貼られていて、そこには4月に南相馬でお世話になった喫茶店「いこい」や居酒屋「日乃本」の名前もあった。インターネットの無料利用コーナーでは中学生らしい女の子が熱心に調べものをしている。 寄付された衣服や食器を自由に持ち帰ることのできるコーナーでは、赤ちゃんを抱いた夫婦がサイズの合う子供服を探していた。
2階には食堂や談話スペースがあって、壁に市内の小学生の寄せ書きや、励ましの手紙が貼られている。この日はボランティア団体が避難所の子どもたちと遊ぶ催しがあって、元気そうなはしゃぎ声が聞こえた。3階以上は居住スペースとなっている。
南相馬市出身のIさん(70代女性)に話をうかがった。「個室で暮らせるのが一番ですね。以前の避難所生活と比べると天国です。食事はコックさんがつくってくれます。 野菜を出してくれるなど栄養のバランスも考えてくれて、取手の人には本当に感謝していますよ。晴れた日には、部屋から富士山も見えるんですねえ。おどろきました」
この避難所は一世帯ごとに個室が割り当てられている。Iさんはいま、家族と四人暮らしだ。玄関を入ると8帖ほどの板の間に所狭しとベッドが四つ並べられ、その奥に8畳の座敷がある。確かに、Iさんが言うように個室で暮らせることは大きい。 3月30日に訪ねたさいたまスーパーアリーナでは、大勢の人がアリーナの広い廊下に近くのショッピングモールから調達したダンボールで申し訳程度の仕切りをつくって生活しており、「プライバシーがなくて辛い」という声を聞いた。 他所ではさらに劣悪な環境で暮らす避難者も多数おり、こうした「避難所格差」は今後ますます広がっていくかもしれない。この施設も元が宿泊所であるとはいえ、やはり四人で暮らすには窮屈そうだ。椅子がないので高齢者は腰に負担もかかる。 慣れない生活環境のために体調を崩し、取手市内の病院へ通う方も少なくないそうだ。
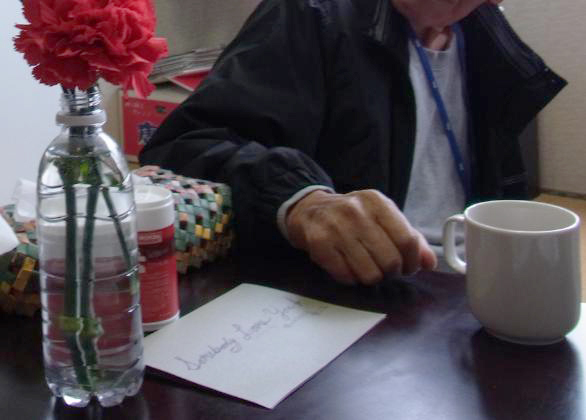
釣りが好きだったOさん(70代男性)は自分の船を持っていたが、津波で流されてしまった。かつて原町沖ではカレイやアヤメがたくさん釣れたそうだ。しかし、それが一昨年の12月からさっぱりダメ。自分だけでなく、釣り仲間は皆そうだったと言う。
「今ァ思うと、魚はわかってたんじゃァねえかな。ンで、みんな逃げちゃったんじゃねえかな」
以前この避難所へ東京電力の社員が訪問した際、福島第一原発の近隣で配電品の会社を営んでいたOさんの胸中は複雑だった。「(東電の社員を)責めてる人もいたけどね。おれァ、東電で食ってたところがあるから。いつ戻れるのかってだけ、聞いたよ」
他県のとある避難所では「避難者の生活態度が悪い」と市の職員から苦情が出たと聞くが、この避難所では食器洗いや掃除を避難所内の各家庭が当番制で担当するなどルールが存在する。
もちろん、南相馬出身の人々といっても誰もがはじめから互いに見知っているわけではなく、困難も多かった。当番の仕事をしない人や物資の配給時に必要以上の量を持って行ってしまう人、食事のときにはまるで「上げ膳据え膳」でボランティアに対する態度が悪い人もいたそうだ。
また、住み慣れた土地へ一刻も早く帰りたい気持ちが募る一方、取手の人に「これからはずっと取手に住むのでしょう?」と言われて気分を害した人もいる。同じ避難所に暮らす人々にも、それぞれの事情と胸の内がある。

避難所は坂を登った先にあるので、買い物へ行くと帰りがつらい。
この避難所には当初100人ほどの人が暮らしていたが、現在は半分ほどに減った。避難所の開放期限も5月末に迫っている。仮設住宅へ入居する人、身内を頼って他の街へ行く人、福島へ帰る人。選択はさまざまだ。小さな子供のいる家族は、早くに取手市内外のアパートや団地へ入居した。
ある人は仮設住宅への入居を申請すると、他の避難者から「自炊しなければならないのに、何でわざわざ。今のままなら何もしなくても食事が出るのだからいいじゃない」と言われて驚いたそうだ。
繰り返しになるが、南相馬の人々に限らず「被災者」や「避難者」の内実は決して一様ではない。それは、我々ひとりひとりに生活があるのと同様だ。毎日血眼になって未だに親族を捜し続けている人もいれば、どれだけの補償を引き出せるか考えている人もいる。 被害の程度についてもそうで、家財道具の一切が津波に流されてしまった人もいれば、大した被害を受けずに済んだ人もいる。そうした、ある意味でごくごく当然のことを忘れてはならない。
震災と原発事故から二ヶ月が経ったが、避難生活を余儀なくされている人々は今後のことを心配している。避難所生活はいつまで続くのか。自宅付近の放射線量はどうなっているのか。もし戻れたとして、そこで安全に暮らしていけるのか。生活補償はどうなるのか。 そうした諸事項について明確なビジョンが示されていないことが、彼らにとっては何よりも不安にして不満だ。彼らが必要としている情報が十分に提供されているとは到底言いがたい。
来年高校受験を控えた中学生のMさんは、福島と関東のどちらの高校へ進学すべきか悩んでおり、福島に帰って暮らせるかどうか、毎日自分で南相馬市の放射線量を調べている。南相馬の中学に通っている友人も多いそうだ。
原発事故に伴う避難への損害に対して東京電力の仮払い補償金の支払いは決定しているが、最近では地元での仕事を解雇されてしまった多くの避難者が茨城県某市のハローワークを訪れている現状もあり、被災者や避難者の雇用についての生活保障はまだまだ行き届いていない。 一方で、先ほどの人のように「今のままなら何もしなくても食事が出るのだから」となれば労働意欲が減退してしまう人が増える懸念もあり、実際に阪神・淡路大震災では深刻な問題となった。長期的な視野での「復興」のために、考えなければならない課題は山積みだ。
先ほどのIさん一家の自宅は先月22日以降「警戒区域」として立ち入りが禁止されている、福島第一原発の半径20キロ圏内にある。取手での避難生活に加え、警戒区域になるとの発表があまりに急だったため、自宅に戻る時間はなかった。 4月上旬に福島第一原発の半径20キロ圏内(南相馬市小高区)を訪ねた際の写真をご覧いただくと、中にはよく見知った風景やご自宅近所の写真もあり、Iさんのご主人は時おり目頭をじっと押さえた。
懐かしい風景の写真とはいえ、それは地震と津波の惨憺たる現状を写したものばかり。それをただ見せることしかできない私は彼らに対してかける言葉がない。それでもIさん一家は「危険なところ現状を見に行ってくださって、ありがとうございました」と言ってくださった。
若い頃からつらいことや悩み事があるといつも海を見て元気を出してきたIさんは、震災の直後にすべてを呑み込んでいく黒い波を見て大変なショックを受けた。 家は水浸しとなり、流されてしまった近所の友人もいる。それでも、住み慣れた地へ一刻も早く帰りたいという想いは変わらない。Iさんはいま、地元南相馬の塩辛が食べたいそうだ。
(文責 : 稲葉秀朗)