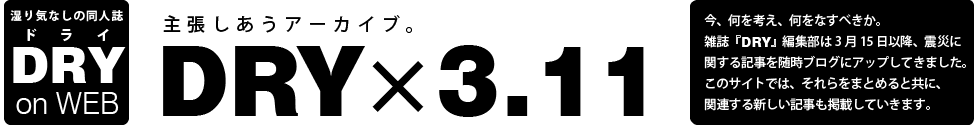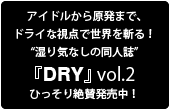福島・南相馬のいま ◎4月7日◎

仙台方面から国道6号線を南下すると立ち入り禁止の看板が立てられていた。原発から20キロの境界線だ。 そこで出会ったフリージャーナリスト西牟田靖氏の持つ放射能測定機は毎時0.61マイクロシーベルトを示す。
人間に影響を及ぼす放射線量は500ミリシーベルト以上であると言われている。 マイクロシーベルトはミリシーベルトの1000分の1であるから、その時の放射線量は毎時0.00061ミリシーベルトだったということだ。 これは「すぐには影響の出ない値」と言って差し支えないだろう。 福島県内のテレビでは地域ごとの最新放射線量がテロップで表示されており、人々はそれらを目安に生活を営んでいる。
今回南相馬を訪れて意外だったこと。まず南相馬沿岸部以外の地域は電気、ガス、水道といったライフラインが問題なく使えたこと。 ガソリン、食糧等の物資も徐々にではあるが入るようになって来ており、不便はあるものの最低限の生活に支障の無い様子だった。
次にそのような状態であることが町を離れ避難していた人々に伝わり、徐々に人が戻りつつあったということ。 もともと7万人が住んでいた同市だが、現在は2万人ほどが暮らしており、個人商店や中心街に2店舗あるセブンイレブンは店を開けている (ただ新聞の個人宅配が中止されており、早朝のセブンイレブンには新聞を求める人々が集まっていた)。
 原ノ町駅前の光景
原ノ町駅前の光景
 原ノ町駅前のセブンイレブン
原ノ町駅前のセブンイレブン
南相馬原ノ町駅前で、「珈琲亭いこい」を営むマスターも、避難所から戻り店を開ける決心をしたひとりだ。
「原発が爆発してから、着の身着のまま市外へ避難した。でも飼い犬の様子が気になって戻ってきた。 そしたら大勢のマスコミが店を訪れて、何か食べ物を作ってくれって言うんだ。材料も何も無かったけど、とりあえず米を炊いておにぎりを握って持たせたよ。」
ただ、「彼らはすぐに居なくなってしまった」そうだ。詳しいことは解らないが、自主的に避難をしたということだろう。
「この辺の放射線量はまだ低いようだし店を開けることにした。出来る限り店は続ける。政府、報道機関に対して言いたいことは、曖昧なことは言わないでほしいということ。 今後我々はどうしたらいいのか、明確な方針を示してほしいと思う。」
 居酒屋「日乃本」
居酒屋「日乃本」
市内の居酒屋「日乃本」はささやかな安堵を求める人々の姿で賑わっていた。物資不足のせいでメニューが少なくなっていることを除けば、ふつうの居酒屋だ。 一家でこの店を訪れていたAさんに話を伺う。双葉町から親戚を頼り避難してきた。いたずら盛りの一歳の長男がかわいい。
「私はね、政府・東京がこの地域を切り捨てようとしているのが解るんですよ。だって普通に考えたらお荷物だものね。賠償金も払わなくちゃならないし、野菜や魚は汚染されてしまっている。 20キロから30キロ圏内を“立ち入り禁止区域”でなく“屋内退避区域”にしたのだって、これ以上賠償額を大きくしないためでしょう?」
東京から福島へ注がれる一部の冷めた視線を、彼は十分に理解しているようだった。私は言葉が無かった。
「子供にとって好ましくない環境であるのは解っています。しかしそう簡単に自分の故郷を捨てることは出来ない。俺は自信を持って自分を“田舎者”だと言いますよ。 田舎には東京人にはわからない暖かさがある。それはコミュニティの暖かさなんです。その居心地の良さは都会人には解らないだろうね。それらを簡単に捨てることなんて我々には出来っこないですよ。」
私はさいたまスーパーアリーナで出会った双葉町出身のおばあさんの言葉を思い出していた。「県外は良く分からない。早く福島へ戻りたい。」
どれだけ避難所生活が快適であろうとも、住みなれた地を離れて過ごす避難者には決して満たされない部分がある。 彼らは多少放射能の危険があろうとも“福島”で暮らしたいのだ。福島沿岸部は高齢化が進んでいる。大きな産業は、漁業、農業、そして原子力産業だった。多くの高齢者は県外で暮らしたことはない。
Aさんはこれからもこの地で暮らしていきたいと仰っていた。「私たちは十分頑張っている。東京では自粛ムードに流されずどんどん金を使ってほしい。金が回ることで少しでも福島が潤えば・・・。」
 小浜地区にて見つけた古写真。翌日市役所へ届けた。
小浜地区にて見つけた古写真。翌日市役所へ届けた。
4月11日、政府は福島第一原発から20キロ圏内への立ち入りを禁止する方針を打ち出した。これまでの避難勧告には強制力がなかったが、その決定の後に無断で立ち入った場合には罰則・罰金も適用されるという。 放射能被害を拡大させないための政府の対策なのだろうが、そこに元住民の意思は存在していない。元住民には現在と未来のふるさとを見続ける権利がある。もちろん、暮らす権利も。臭いものにふたをするのは簡単だ。 しかし一度ふたをしてしまえば、それは“タブー”になる。そしてそれは福島への差別感情と繋がりかねない。
「うちの娘は、出身が南相馬だって言ったら結婚出来なくなるんじゃないかって言ってたよ。」我々を20キロ圏内へ案内してくれたTさんの言葉だ。
南相馬を訪れた我々を皆さんは大いに歓迎してくれた。そしてたくさんの話をしてくれた。もはや大手マスコミがあまり足を運ぶことの無いこの地域で、彼らは日本から取り残される疎外感を感じていたのだろう。
震災から一カ月が経ち東京は落ち着きを取り戻したが、同時に被災地への関心も薄れている気がしてならない。我々は今後も南相馬へ向かい、現地の状況、地元民の思いをリポートしていこうと思っている。
(文責 : 編集部 斉藤光平 | 写真撮影 : 稲葉秀朗)