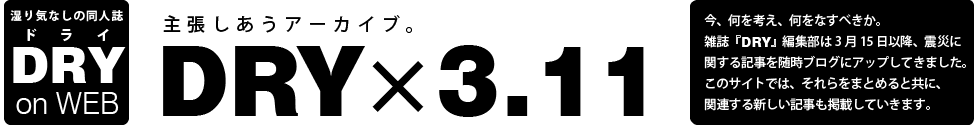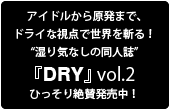埼玉・さいたまスーパーアリーナの様子 ◎3月30日◎
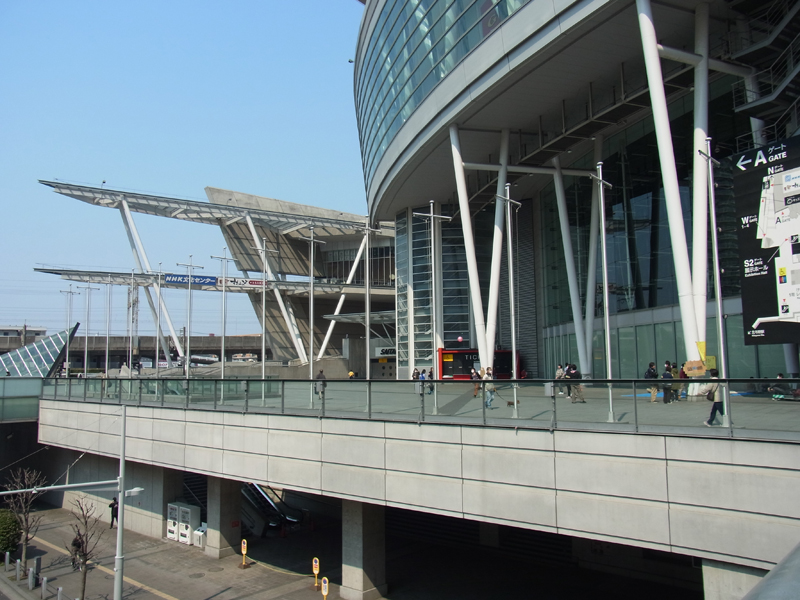
3月30日、東日本大震災の避難所として解放されたさいたまスーパーアリーナを、編集部の斉藤と本誌読者のKさんと共に訪れた。本施設の避難所としての解放期限は明日に迫り、すでに次の避難所へ移動を始めた避難者も多い。
入り口付近までやってきてまず驚かされたのは、集まったボランティアの数。信じられないことだが、裁ききれなかったボランティア志願者が、整理番号をもらって外で待機しているのだ。 明朝八時頃にはすでにボランティアの受付を打ち切り、早くから並んだが何もできず帰った人もいるという。
「物資と人が集まりすぎてしまった」と語るのは、さいたま市都市整備部の職員だ。「物資は他の避難所でも再利用できても、人についてはどうしようもありません。こうした避難所間の格差は、今後も広がると思います。 さいたまスーパーアリーナは交通アクセスも便利ですから、ある意味で地の利がよすぎたのです」かくして、さいたまスーパーアリーナは、首都圏やその近郊で、何らかの形で今回の震災に関与したいと願う人々を一手に集めることになったのだった。
阪神・淡路大震災の際にボランティアとして被災地へ赴いた方がみな口を揃えて言うことは、「ボランティアスタッフはきちんと組織化されていることが肝心」ということ。 確かに、指揮系統が確立されていない以上は、せっかく大勢のボランティアが駆けつけたところで烏合の衆である。しかし、一方で裁ききれない志願者があぶれてしまうのもまた本末転倒だ。
本施設には3月19日に到着した双葉町の町民ほか、千葉や茨城からの避難してきた人も暮らしている。避難所の中の様子を見てみよう。入り口付近の掲示板には被災者の就職支援、在室介護、ペットの散歩代行、予備校による受験生のための施設開放、 理髪店による無償の洗髪・散髪、土木工や舗装工の求人といった、多くの告知が貼られている。糖尿病あるいは血糖値が高めの人は、スポーツドリンクを飲むと症状が悪化する可能性があるので注意されたしといったものまである。
主な居住スペースはメインアリーナをぐるりと囲む2階の廊下部分だ。人々はここに敷かれたブルーシートや毛布の上に段ボールで申し訳程度の仕切を立てて生活している。 段ボールは近くのショッピングモールから調達したものだ。配られる食事はカップそば、パン、水、ヨーグルトなどで、野菜や果物はあまり見かけなかった。
ところどころに食料や飲料を配るブース、携帯電話の無料充電コーナー、足湯やマッサージといったサービスコーナー、段ボールでつくられた簡易女子更衣室、子供の遊び場や学校、読み古した本や雑誌を段ボールに詰めた「ミニ図書館」などが設けられ、まるで小さな街のようだ。 壁に目を転ずると避難者をはげますメッセージや伝言板、医者の往診に関する告知、次の避難所の案内、退去する際の注意事項など多くの張り紙がされている。
3階、4階にはさいたま市役所による住宅や雇用、被災者支援基金等の各種相談窓口が設けられている。各階の移動は基本的に階段で、車椅子を利用する人の移動や物資の運搬には機材搬入用のエレベーターが用いられる。
我々は、双葉町から避難してきたMさん(70代女性)に「住宅相談窓口へつれていってもらいたい」と頼まれた。彼女は車椅子がなければ動けないので、普段は外へ出ることもせずに自分のスペースでじっとしているそうだ。 床の上での生活は疲れるし、プライバシーはほとんどない。近くに知り合いがいるわけでもないから話し相手もいない。集団生活は限界、次の避難所も行きたくない、とはっきり仰った。
避難所の警備員から住宅相談窓口は4階にあると聞いて行ってみると、「今日から3階へ移動した」という。仕方なくエレベーターで移動しようとすると、今度は建物の構造上3階ではエレベーターから降りることができない。最終的に、介護スタッフに協力を頼んで2階から3階まで階段で上がった。
彼女の相談内容は、一刻も早く福島に戻りたいので、福島県内で仮設住宅や一時的に滞在できる場所を探したいとのことだった。しかし、この相談窓口はさいたま県内で住宅を探す人のためのものだった。 「福島県に問い合わせてもらいたい」の一点張りの窓口と、「情報があれば知らせてほしい」という彼女の間にしばらく問答が続いた。
彼女は、福島県内のホテルや旅館が被災者・避難者を無償で受け入れるという情報も得ていたので、そうした旅館やホテルを調べるにはどこへ問い合わせたらいいかとも尋ねたが、これも窓口では管轄外なのでわかない。 仕方なく代わりに我々が福島県の災害対策本部へ問い合わせたが、「それについてはここへ聞いてくれ」と、福島県の観光協会やらどこが管轄しているのかもよくわからない復興基金なる組織やらをたらい回しにされた挙げ句、「各市町村ごとに災害対策本部があるので、そこへ直接たずねてくれ」とのこと。 結局、この時点ではたとえば「避難者受け入れ可能施設一覧」のようなリストが出来ているわけではなく、情報は集約されていなかったのだ。
よく役所の仕事は「縦割り行政」や「セクショナリズム」などといわれるが、まさにその弊害を目の当たりにした気分だった。もちろん、自らの管轄部門に全力を挙げて取り組んでおられる職員の方々には頭が下がるばかりだ。 そもそも平時における役所の仕事においては縦割りであるほうが円滑に進むものもあるだろう。しかし、一方で今後万が一の場合に備えて、緊急事態におけるセクショナリズムの克服策も講じておく必要はある。
彼らもこうした「縦割り」の弊害は重々承知しておられるようで、それが気の毒だ。もう一つ例を挙げよう。さいたまスーパーアリーナは3月11日の震災発生直後、帰宅困難者のために解放された。 こうした前例もあったため、原発事故に伴い福島県知事より全国の都道府県に避難者の受け入れ要請があった際、埼玉県はスーパーアリーナを解放することを決定した。3月16日のことだ。 しかし、これはあくまでスーパーアリーナを管理するさいたま市の都市整備部の判断で、この時点では食料の確保やボランティアの手配までは済んでいなかった。
プレスリリースに際して毛布のみの提供、という但し書きがついたときにはクレームが殺到してしまったそうだ。このあと、都市整備部は福祉部と連携して災害対策本部を立ち上げ、福祉部がボランティアの指揮や食料の手配を行うことができたそうだ。 結果的に、避難者の受け入れは準備万端の状態で、というわけではなく、受け入れと避難所の環境整備は同時進行で行われることとなった。この話を聞かせてくれたさいたま市の都市整備部の職員は「いやあ、縦割りというのがどうも問題でして・・・」とため息をついた。
先ほどのMさんは、双葉町でなくとも、せめて福島でいいから帰りたい、と繰り返しておられた。Mさんは明日から騎西高校へ移るそうだ。いやだ、いやだ、と繰り返すMさんを見ながら、 当座の避難生活が確保されていることが彼らにとって何ら状況の改善を意味するものではないということを痛感した。彼らは一刻も早く、自分の暮らし馴れた土地へ戻りたいのだ。
斉藤によると、双葉町は震災前から高齢化が進んでいたそうだ。実際、アリーナの中でもお年寄りの姿を多く見かけた。談笑する人もいれば、じっとして何かを見つめている人もいる。 テレビの前では、人々がみな原発のニュースに見入っている。テレビの画面越しにしか故郷をみることができないのは、さぞ辛いことだろう。
さいたまスーパーアリーナを後にした我々は、最寄りのさいたま新都心駅へやってきた。駅前は人々がせわしなく行き交い、一時の混乱を思えば首都圏では「日常」が戻りつつあった。 駅前から、スーパーアリーナがみえる。我々は、あそこで暮らす人々が未だに「非日常」の中にあることを決して忘れてはならない。
(文責 : 稲葉秀朗)