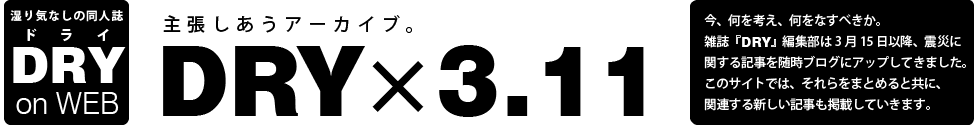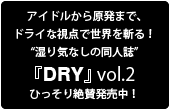インド・その日、遠い国から日本を眺めて ◎3月11日◎

3月11日、ニューデリーの幹線道路で、僕はバイクに跳ねられた。青ざめた顔で慌てふためく親父の挙動が非常に愉快だったことを覚えている。頑丈な体に産んでくれた親に感謝せねばなるまい。丁度、陽も暮れてきた頃だったので、宿屋にチェックインし、インドが如何にエキゾチックで騒々しくてばっちい国かということと、 旅行1日目にして交通事故に遭うという面白イベントに遭遇できたエピソードを、日本の家族と友人に伝えようと電話屋台(公衆電話はほとんど存在しない)に行って国際電話をかけてみた。しかし、どの店でも一向に繋がらない。チッ。所詮インドか。 電話線すらまともに整っていないのも、しかし、この街の世紀末世界感を見ると理解はできる。だが一方で流石IT大国と言われるだけはあり、ゴミだらけの街中にはネットカフェをよく目にすることができる。日本語入力可能なネットカフェを見つけて、とりあえずtwitterに接続してつぶやいた。
"インドでバイクに跳ねられたなう"
さて、これから今日一日をどう面白おかしく書き起こそうか…そんな事を考えていると、どうも皆のつぶやきの様子がおかしい。異様に流れも速い。
"どしたの。もしかしてやばい系?"

かくして、僕は、あの震災の日とその後の2週間を――混乱を極める日本を、日本人でありながら、外から眺める立場にあった。東日本大震災を多角的な視点から眺めるこのサイトをより充実させるために、あの時の奇妙な体験と僕の感じた印象をここに記したい。 あの激動の半月を体験しなかった僕の言は、地震で苦労をされた方からすると不快に感じる部分もあるかもしれないが、敢えて、自分が感じたことを正直に書こうと思う。これもまた、ひとつの現実なのだ。
次の日にもなると、インド国内でも日本の震災の惨事は知れ渡っていた。テレビニュースのヘッドラインはずっと津波の映像を流しているし、新聞の一面は被災地の惨状を映した写真がおおきく載っていた。正直、僕は、あの映像が日本で起きていることを信じられなかった。理性的に信じられないのではない、逆なのだ。まるで遠くの知らない国で起こった災害のような感覚がしてならなかった。
日本国内ですら情報が混乱していたのだから、インド国内の情報の錯綜ぶりは凄まじいものであった。ある日は、宿屋の親父に「おいジャパニーズ!日本で原発が大爆発したぞ!」とか言われて、あわててネットカフェを探して事実確認をしたこともあった。


出会う外国人は皆すごく心配してくれるし、心から同情もしてくれた。だが、そんなやりとりと通して僕が強く感じたことは、日本人と外国人の震災に対する認識の違いだ。もちろん、そのズレの原因のひとつに、インド国内で噂として広まる過程で日本の被害状況が過大なものになり、 間違った情報が蔓延していたという理由もあるだろう。だが、それだけでは説明がつかないほどに、日本人と外国人の間で認識のギャップがあった。特に欧州人の旅行者達からは「なんでジャパニーズはこんな状況でも次の日から普通に会社に出て働いているんだ!?クレイジーだ!!」と何度も言われた。 インド人達からは「暫く日本には帰れないから大変だろう。え!?帰るのかい!?マジで!?」と驚かれた。一方で、感情をあらわにして日本の地震被害を語る外国人の傍ら、日本人の旅行者は、あっけらかんとインドの観光地について語り合っていた。外国人が地震と放射能に臆病すぎるのか? 災害に動じない日本人のハートが強いのか?それともただ危機意識に欠けているだけなのか?いずれの理由付けも僕はしっくりこない。あの時あの国では、傍観者たる外国人は当事者たる日本人以上に当事者的感情を持っていて、当事者たる日本人は傍観者たる外国人以上に傍観者的感覚を持っていたとことは確かだったと思う。
実際、日本人旅行者と話をすると誰もが口を揃えて「まるで他人事のような気がして実感がわかない」と、後ろめたい表情をして言う。僕もそうだ。先にも書いたが、理性ではなく、感覚の部分で、自分の国で起こったこととは思えないのだ。 チリの震災やスマトラ沖の津波の時のような感覚だ。僕を含め、多くの日本人はそんな感覚に罪悪感をもっていたと思う。
僕がその奇妙な感覚のズレを治せたのは、帰国したその日。暗い空港と、カップラーメンの置いていないコンビニを見てからだった。
そんな、日本人でありながら奇妙な傍観者的感覚を抱えた僕は、地震後の情報の混乱を、ある意味、冷めた目で見ることができたと思う。
僕が日本の情報を知る手段はほぼインターネットに集約されていたが、ネット上での稚拙なデマの交錯っぷりは珍妙だとすら思えた。パニック状態に近い人間の心理なのだから仕方が無い、と思う一方で、 今回の地震のデマ情報の盛り上がりっぷりには、ネットメディアの台頭と、それに悪い意味で毒されてしまった愚かな若者達の存在があると思う。
我々一市民は、遠く離れた地域の状況や、高度な専門知識がないと知りえない情報の正誤を、いかにして知ることができるのか?否、結局、このような場合、我々が絶対的真実を知ることは大抵無理なのだ。当然のことだ。 ところが、ネットという、これまでのメディアを遥かに越える雑多な情報を擁す存在の出現で、そんな当然のことを理解できていない人間が増えたように思える。情報の選択肢が膨大になった結果、その中で「自分の信じたい情報だけを取り入れて」それを真実とする人が増えたのだ。 言うなれば、情報の偏食である。確実に信頼することはとてもできないが、それでも、日本国内だともっとも信用性が高いと思われるテレビや新聞といったメディアの情報に耳を閉ざし、自分にとって都合の良いネットに転がる情報を信じる人間が、どんなに増えたことか。 遠隔地や専門的知識を必要とする情報は「~らしい」の粋を出ることはほとんど無い。その「~らしい」という不確かな情報を抱えた上で、どう行動していくかが重要なことではなかろうか。
インドで遠き日本の地の混乱を眺め、もっとも奇妙に、そして危うく思った事は、そんな現象だった。

最後にもうひとつ、インドの地で気付いたことがあった。それは日本の治安や衛生、福祉など社会制度の良さだ。日本国内にいると大企業やら政治家やらの私欲に塗れたスキャンダラスな情報が日々流され、特にこういう災害時において、日本人の自国の社会環境に対する不満は募るばかりだろう。 しかし世界に目を向けてみると、やはり、今の日本よりも辛く厳しい環境の暮らしを常に強いられながらも、明るく前向きに生きている人々は数え切れないほどたくさん存在するのだ。無論、我々は今も厳しい状況におかれる被災地の方々を助けなければならない。異論を挟む余地もない当然のことだ。 でも、心に留めておくべきだ。いつまでも我々は悲劇のヒロインぶっていてはならないし、この混乱期において体制批判を繰り返す駄々っ子であってもならない。日本を立ち直らせるのは他でもない我々なのだ。世界的に見たら、現在の環境はまだまだ恵まれているのだから、座り込んではいられない。
震災を経て3ヶ月。そろそろ、立ち上がれた者は、先を見据えて、自分の足で走り出さなければならない時期だと思う。
(文責 : ヨッケ・コンドオ)